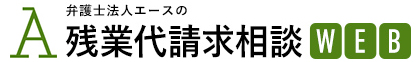賃金払いの5原則とは?
労働基準法は,使用者から労働者への賃金支払いについて厳格な制約を規定しています。
具体的には,賃金は,「①通貨で(通貨払い原則),②直接労働者に(直接払い原則),③その全額を(全額払い原則)支払わなけばなら」ず(労働基準法24条1項本文),「④毎月一回以上(毎月一回払い原則),⑤一定の期日を定めて(一定期日払い原則)支払わなければならない」(同法24条2項)とされています。これだけ短い文章で5つもの原則を盛り込む規定も珍しいですね。
この賃金支払いに関する5つの原則はとても厳格な原則であり,これに違反した場合には30万円以下の罰金(刑事罰!)が科せられます(同法120条1号)。賃金の支払いは労働者にとって文字通り死活問題ですので,このように非常に厳格な制限が設けられているのです。
賃金直接払いの原則とは?
賃金直接払いの原則とは,賃金は労働者本人に直接支払わないといけないということです。したがって,労働者が未成年者である場合に親権者に払ったり(同法59条),労働者が成年被後見人である場合に後見人に払ったり,あるいは労働者の任意代理人に払ったりすることはできないとされており,そのような行為は無効になります。
その趣旨は,賃金の中間搾取(ピンハネ)を防止して,労働者に直接に労働対価を支払わせる点にあります。
労働者から任意に賃金授受の代理権を与えられた者への支払いも禁じられているということです。そもそも,そのような代理権を与える行為が無効と解されています。
さらに,労働者が賃金債権を債権譲渡した場合であっても,使用者は債権の譲受人ではなく労働者に対して賃金を払わないといけないとされています(最高裁昭和43年3月12日判決 電電公社小倉電話局事件)。
なので,親権者だからとか,委任状を持っているから,債権譲渡の通知があったから等の理由によって,うっかり労働者以外の者へ支払ってしまうと,もう一度労働者から賃金請求された場合には使用者としは払わざるを得ないというリスクがあるだけでなく,罰金30万円に処せられるリスクもあることになります。
賃金直接払いの原則の例外
ただし,原則には例外がつきものですよね。賃金直接払い原則にも例外があります。
代表的なものとして,給与債権が差し押さえられた場合に,差押債権者に任意に支払う場合は例外に当たるとされています。債権譲渡の場合はNGだけど,差押されているなら仕方ないということですね。
また,行政解釈(通達)によって,使者への支払いは直接払い原則に違反しないとされています。例えば,秘書を使いに出して給料を取って来させたり,病気中に妻に取りに行かせたりすることは適法とされます。
ただ,現実問題としては,使者と代理人の区別はかなり難しいでしょう。よく,本人に支払ったのと同一と評価できるかどうかという基準にならないような基準が述べられることがありますが,使用者側からすると,二重払いのリスクと刑事罰を科されるリスクがあるので,使者に対しても支払いを躊躇してしまうのが普通でしょうね。
弁護士の預り金口座に賃金を支払うことは直接払い原則違反となるか?
さて,やっと本題です。賃金の未払いというのは,労働問題ではよくある紛争形態です。単純に給与が支払われないという場合もありますが,多いのは,残業代や深夜割増手当などの部分が支払われていなかったり,解雇が無効だから解雇後の賃金を払えという形で争われることもあります。
このような場合,労働者としては,弁護士に依頼をして会社と交渉してもらい,未払い賃金を回収するということがあり得ます。
通常,弁護士が相手方と交渉して金銭の交付を受ける場合には,弁護士の預り金口座を支払い先として指定することが圧倒的に多いのですが,この場合に使用者が弁護士預り金口座に賃金の支払いをすることは直接払い原則に反しないでしょうか(ちなみに振り込みによる支払いという意味では通貨払い原則に反しないかも問題となります。)?
反しません。と言いたいところですが,上で述べたように,直接払い原則は労働者から任意に賃金授受の代理権を与えられた者への支払いも禁じていると解釈されているため,形式的にはこれに反していると言わざるを得ないところです。
そうだとすると,直接払い原則に反するので弁護士の口座には振り込めない,あくまでも本人の口座に振り込みますと主張する使用者が出てくる可能性もあります。それならそれでいいじゃん,と言われてしまうとあれなのですが,弁護士としては,できれば,預り金口座に入れてもらった上で報酬を清算して本人に返したいという思いがあるのが通常です。そこで,代理人である弁護士の預り金口座への支払いが直接払い原則に反しない理由を考えてみたいと思います。
賃金支払いではないとの説明
賃金の支払いに関する問題だけでなく,不法行為に基づく損害賠償請求を含めたあらゆる紛争は,最終的には示談や和解で終結することが圧倒的に多いです。その際に支払われる金銭については,元の債権が賃金支払請求権であろうが,慰謝料請求権であろうが,売買代金請求権であろうが,損害賠償請求権であろうが,「解決金として」とか「示談金として」支払われることがほとんどです。
したがって,最初は賃金支払い請求から始まった紛争であっても,解決時には「解決金」のようにその金銭の法的性質をいわば透明なものに昇華した上で支払ってもらうことが多いのです。
このような場合には,そもそも使用者から支払われるものが賃金ではなく「解決金」であるといえますので,賃金直接払い原則には違反しないということになります。
本人に支払うのと同一とみなせる状況である
使者に支払うことが直接払い原則に反しないというのと同じ理屈ですね。そもそも弁護士は,賃金受領の代理権だけを本人からもらった訳ではなく,使用者と交渉する権限などの権利実現のために必要な全ての権限を本人から与えられているものです。また,弁護士はその職務を遂行するに当たって,多くの義務を課されており,弁護士がクライアントである労働者の賃金を不当に搾取するようなことは考え難いところです。
そうであれば,弁護士に支払うことは本人と支払うことと同一とみなせるのではないでしょうか。
説得力に欠けますか?
それでは,本人の真摯な同意があるためという理屈はどうでしょうか?直接払い原則についてではないですが,全額払い原則に関して,次のように判示した最高裁判例(最高裁平成2年11月26日判決)があります。
一 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)二四条一項本文に違反しない。
二 甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をし、甲会社が、乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつて乙の有する退職金債権等と相殺した場合において、右返済に関する手続を乙が自発的に依頼しており、右貸付けが低利かつ相当長期の挽割弁済の約定の下にされたものであつて、その利子の一部を甲会社が負担する措置が執られるなど判示の事情があるときは、右相殺は、乙の自由な意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効と解すべきである。
全額払い原則の例外要件として,「右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき」と定めている点に注目してください。
この場合には,全額払い原則の趣旨に反しないということですね。この理屈は,直接払い原則にも応用できるはずです。
直接払い原則の趣旨が,中間搾取の禁止にあることからすれば,そもそも賃金が支払われていない(と労働者が考えている)状況で,その労働者が使用者からの賃金回収を依頼した弁護士に対しての支払うことに同意しているのであれば,それはまさに「同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき」といえるのではないでしょうか。